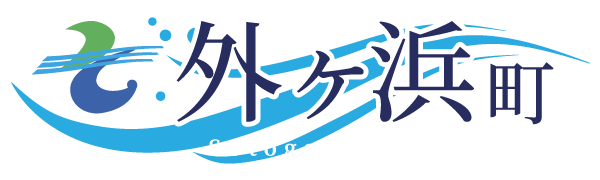世界文化遺産 史跡 大平山元遺跡とは
更新情報
|
2025年7月18日 |
各種資料を追加しました。 |
|---|

大平山元遺跡

大平山元遺跡遠景
列島各地との関係性を示す石器が多く見つかる希少な遺跡
史跡「大平山元遺跡」は、石器の材料となる岩石(珪質頁岩)が採取できる蟹田川の近くにあります。後期旧石器時代後半期から縄文時代草創期まで、石器などの特徴の移り変わりを追うことができる遺跡です。
旧石器時代の石器などの特徴では、主に関東地方や中部地方で見られる石器、北海道で流行した石器、西日本との関係がある石器などが見つかっています。これらのような日本列島各地との関係性を示す石器が多く見つかる遺跡は、北日本では他に例がありません。縄文時代草創期では、無文土器片が見つかり、石鏃(矢じり)や大型の石刃(ナイフの素材)のまとまりなどがあります。

大平山元遺跡出土遺物
「1万5千年以上前の土器片」縄文時代という新しい時代へ
北海道・北東北の縄文遺跡群の関わりについては、史跡の本質的な価値のなかでは、道具の移り変わり、土器を生み出し、年代が判明しているところが大切です。年代は、土器片に付着していた炭化物を分析し、今から約1万5千年以上前に使われことがわかっています。煮炊きに使った土器がみつかり、定住のめばえがわかる遺跡です。弓矢も使われはじめ、縄文時代という新しい時代へ変わっていく様子がわかります。

無文土器片
「縄文遺跡群」1万年以上にわたる定住の発展と成熟
ユネスコ世界遺産「北海道・北東北の縄文遺跡群」は、採集・漁労・狩猟を生業に1万年以上も続いた人々のくらしや精神文化を今に伝える貴重な文化遺産です。日本列島北部では、ブナ・クリ・クルミなどの森林資源や暖流・寒流が交わる海域が育んだ水産資源を背景に、今から約1万5千年前に定住がはじまりました。その後、1万年以上にわたり農耕に移行することなく、採集・漁労・狩猟による定住を発展・成熟させました。この間、精緻で複雑な精神文化も育まれ、環状列石や周堤墓などの祭祀・儀礼の場も充実しました。17の遺跡で構成されており、6つのステージ、定住の開始(1居住地の形成2集落の成立)定住の発展(3集落施設の多様化4拠点集落の出現)定住の成熟(5共同祭祀場と墓地の進出6祭祀場と墓地の分離)にわけられ、大平山元遺跡は、その最初のステージに位置づけられています。
大平山元遺跡 ー史跡指定までのあゆみー
中学生が拾った石器がきっかけで「無文土器片」が発見
大平山元遺跡は、1971(昭和46)年、町内の中学生が拾った石器を契機に青森県立郷土館によって学術調査が実施されました。大平山元Ⅰ遺跡と名付けられ、拾われた石器が神子柴(みこしば)形石斧だったこともあって、担当者の三宅徹也氏の想定どおりに無文土器片が見つかり、神子柴(みこしば)・長者久保(ちょうじゃくぼ)石器群に土器が伴うことを明らかにした考古学史上、重要な結果を示した調査でした。さらに、発掘調査中の住民の情報や踏査によって、大平山元Ⅱ遺跡、大平山元Ⅲ遺跡と遺跡が発見され、続けて学術調査が行われました。ナイフ形石器やいわゆる有樋尖頭器(ゆうひせんとうき)や舟底形の細石刃核(さいせきじんかく)等いくつかの石器群が確認されました。県内の旧石器時代解明をリードする大きな成果を得ることができました。

拾われた御子柴型石斧
幾度の調査を経て国の「史跡」へ
また、大平山元Ⅱ遺跡は、地区会館の建替による発掘調査により、湧別(ゆうべつ)技法による細石刃石器群の接合資料が見つかり、日本列島各地との関係を示す、北日本では他に例がない遺跡となりました。その後、住宅建設に伴って大平山元Ⅰ遺跡の発掘調査を調査団(団長 谷口康浩氏:國學院大學文学部)が行い、土器に付着していた炭化物の年代測定を実施、較正(こうせい)年代を示し、その年代や土器の出現等について問題を提起しました。
続く町教委の学術調査により範囲や価値付けが行われ、大平山元Ⅰ遺跡の範囲全てと大平山元Ⅱ遺跡の一部の範囲が、大平山元遺跡として2013(平成25)年に国の史跡として指定されました。資料は、青森市の青森県立郷土館と外ヶ浜町大山ふるさと資料館で見ることができます。なお、大平山元Ⅰ遺跡の資料は、郷土館学術調査と調査団発掘調査一式が、2019(平成31)年4月に県重宝指定を受けています。

2019年に無文土器片が県重宝に指定
【用語説明】
※1 神子柴形石斧(みこしばがたせきふ)
縄文時代はじめの頃の、全体の型は打製、刃の部分だけを研磨するなどの特徴的な石斧。長野県の神子柴遺跡から見つかった石斧に由来。
※2 神子柴・長者久保石器群(みこしばちょうじゃくぼせっきぐん)
縄文時代はじめの頃の神子柴型石斧や石刃素材のナイフ等を特徴とし、土器が伴うこともある。神子柴・長者久保文化とも言う。長野県の神子柴遺跡と青森県の長者久保遺跡に由来。
※3 石刃(せきじん)
旧石器時代を特徴づける、長さが幅の倍以上あるもの。薄く短冊のような形で連続的に作る。割られて残った方は石刃核という
※4 有樋尖頭器(ゆうひせんとうき)
旧石器時代の後半期の頃、主に両面を加工した石槍(尖頭器)の1側縁に沿った縦長の割れ(加工)を作るもの
※5 細石刃(さいせきじん)
旧石器時代の終わり頃に発達し、各地で独特の作り方(製作技法)があるものの、長さ2、3センチ、幅1センチほどの小さな石刃を連続的に作る。割られて残った方を細石刃核という
※6 湧別技法(ゆうべつぎほう)
細石刃の作り方の種類のひとつ。北海道北部を中心に本州まで広範囲に見つかる。両面を加工した石器の1側縁を側縁に沿って剥ぎ取るように割り、その割れ面から、短軸方向に向きを変え細石刃を連続的に作る。
※7 較正年代(こうせいねんだい)
炭素を含む有機物の年代を測定する14C年代測定値を暦の年代にプログラムを使って算出した年代。
各種資料
- むーもん館年報第1号
 (3846KB)
(3846KB) - 大平山元遺跡整備報告書
 (40549KB)
(40549KB) - 大平山元2011
 (12869KB)
(12869KB) - 大平山元遺跡保存管理計画
 (12332KB)
(12332KB) - 史跡大平山元遺跡整備基本構想
 (12462KB)
(12462KB) - 史跡大平山元遺跡整備基本計画
 (23835KB)
(23835KB) - 大平山元遺跡世界遺産登録記念リーフレット
 (2824KB)
(2824KB)
動画コンテンツ
▶県重宝「大平山元遺跡出土品」(1:26)![]() 外ヶ浜町WEBサイト
外ヶ浜町WEBサイト
▶大平山元遺跡ガイド動画(14:29)![]() 外ヶ浜町Youtubeチャンネル
外ヶ浜町Youtubeチャンネル
▶大平山元遺跡空撮映像(5:17)![]() 外ヶ浜町Youtubeチャンネル
外ヶ浜町Youtubeチャンネル
所在地情報
大平山元遺跡(連絡先は外ヶ浜町教育委員会)
青森県東津軽郡外ヶ浜町字蟹田大平山元(大平山元遺跡展示施設むーもん館向かい)
電話 0174-31-1236 FAX 0174-31-1234
大平山元遺跡展示施設むーもん館
青森県東津軽郡外ヶ浜町字蟹田大平沢辺46-4
電話・FAX 0174-22-2577
アクセス
・JR津軽線蟹田駅から車で10分
・北海道新幹線奥津軽いまべつ駅から車で15分
・青森空港から車で60分
・東北自動車道青森ICから車で45分
大平山元遺跡ガイド
大平山元遺跡もりあげ隊「登録ガイド」が遺跡をご案内いたします。(要予約)
ガイドの予約方法などは下記のリンクをご覧ください。
大平山元遺跡もりあげ隊
大平山元遺跡もりあげ隊は、令和元年に町内の有志で結成された遺跡活用団体で、令和6年4月に法人格を取得し、一般社団法人に移行しました。
もりあげ隊は、大平山元遺跡展示施設むーもん館のミュージアムショップの運営や、お土産品の開発。遺跡ガイド・体験工房の運営、SNSでの情報発信などを行っています。
いろいろな業種が集まったメンバーがそれぞれの得意分野を生かした活動を行っています。
活動の内容は、むーもん公式Xでつぶやいていますので、ぜひご覧ください。

大平山元遺跡もりあげ隊キャラクター「むーもん」
「むーもん」は大平山元遺跡から見つかった「無文土器」とムササビをあわせて生まれた、大平山元遺跡もりあげ隊のキャラクターで、無文土器の帽子をかぶっています。


外ヶ浜町役場 本庁
青森県東津軽郡 外ヶ浜町字蟹田高銅屋44番地2

外ヶ浜町役場 平舘支所
青森県東津軽郡 外ヶ浜町字平舘根岸小川251番地
外ヶ浜町平舘交流センター内

外ヶ浜町役場 三厩支所
青森県東津軽郡 外ヶ浜町字三厩新町18番地1