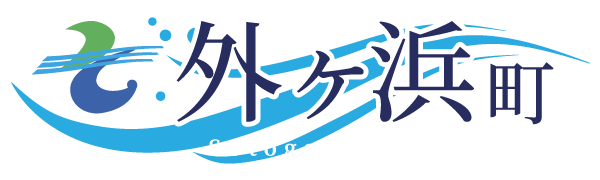学校要覧
外ヶ浜町立三厩中学校
〒030-1729 青森県東津軽郡外ヶ浜町字三厩下平5-1
TEL.0174-37-2042/FAX.0174-37-2504/E-mail:ed.sch.minmaya-c@town.sotogahama.lg.jp
校 訓
健康 自治 友愛
学校の概要
1 学区(三厩地区)の概要
平成17年3月28日、三厩地区(旧三厩村)は蟹田・平舘と合併し外ヶ浜町となる。津軽半島の最北端に位置し,北は津軽海峡を隔てて北海道と相対している。西は半島の中央を縦走する津軽山地を挾んで北津軽郡中泊町と隣接し、南は今別町に接している。年々過疎化が進み、学区の人口は1,369人(令和5年3月末現在)となっている。
2 校章の由来
源義経の伝説を秘める竜馬山義経寺の紋所の笹りんどうに,漁船のイメージを重ねて「中」の文字を図案化した。愛郷心と,義経のように自分の道を切り拓いていく闘魂を身に付けるようにという願いが込められている。旧三厩中学校創立10周年(昭和32年12月29日)を記念して作られたものを,統合した三厩中学校で受け継いだ。
3 生徒・保護者について
(1)生徒数
| 区分 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 合計 |
| 男子 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 女子 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 合計 | 0 | 4 | 5 | 9 |
4 学校の沿革
| 年度 | 月 | 日 | 概要 |
| 平成7 | 4 | 1 |
三厩村立三厩中学校と三厩村立宇鉄中学校が合併統合 初代校長:柳田靖行 氏 着任 |
| 4 | 7 |
三厩村立三厩中学校開校式(新校旗、校歌、校章制定) 在籍:1年28名、2年32名、3年46名、計106名 |
|
| 平成8 | 4 | 1 | 新校舎へ移転完了 |
| 9 | 14 | 体育館竣工式 | |
| 平成9 | 11 | 27 | 修祓式、竣工落成式典(体育館) |
| 平成10 | 4 | 1 | 第二代校長 佐藤一東 氏 着任 |
| 平成12 | 4 | 1 | 第三代校長 蠣崎成徳 氏 着任 |
| 平成15 | 4 | 1 | 第四代校長 田村英二 氏 着任 |
| 平成16 | 10 | 10 | 統合10周年記念式典 |
| 平成17 | 3 | 28 | 町村合併により、外ヶ浜町立三厩中学校となる |
| 平成18 | 4 | 1 | 第五代校長 久保田公浄 氏 着任 |
| 平成20 | 4 | 1 | 第六代校長 花田 裕 氏 着任 |
| 平成23 | 4 | 1 | 第七代校長 成田 徹 氏 着任 |
| 平成26 | 4 | 1 | 第八代校長 山谷 寿 氏 着任 |
| 平成27 | 10 | 17 | 統合20周年記念式典 |
| 平成28 | 4 | 1 | 第九代校長 三浦博英 氏 着任 |
| 平成31 | 4 | 1 | 第十代校長 横山公一 氏 着任 |
| 令和5 | 4 | 1 | 第十一代校長 目時聖児氏 着任 |
学校経営の方針
1 経営の基底 「教育は人づくり」
教育は、人づくりの視点に立ち、知・徳・体の調和のとれた生徒を育成することを目的とし、社会の一員として未来を切り拓くための資質・能力を育成するという役割を担っている。
ここで求められる資質・能力とは、教師が教えることによって身に付けさせるものではなく、子ども自身が自ら学ぶことを通して身に付けていくものであると考える。
したがって、学校は、生徒が資質・能力を獲得しようとする営みを、保護者・地域と一体となってサポートしていかなければならない。生徒が自ら課題を探し、考え、その解決に向けて様々に実践し、振り返り、よりよい方法を見出そうとする経験を積み、価値のある資質・能力が身に付けられるよう、「生徒自らが学ぶ場」をより多く創出できる学校を目指したい。
そのために、われわれ教員は、生徒を尊重し、見守り、生徒の努力の過程や結果をともに喜ぶ、「安心感を与えられる大人」でありたい。また、安心感を与えられる教職員がいれば、保護者も安心して子どもを送り出せるはずである。安心感は、保護者や地域にとって信頼につながる。安心感や信頼を土台として、保護者や地域の声に真摯に耳を傾け、協働して生徒の育成に取り組むことができれば、教育の相乗効果が期待できると考える。
2 学校課題
(1)レジリエンスの育成
(2)基礎学力の定着と個の伸長
(3)学校再編を踏まえた教育活動の再考
3 校訓
「健康」 「自治」 「友愛」
4 教育目標
自ら学び 互いを思いやり たくましく生きる
5 努力目標 目指す生徒像
学:目標を持ち 主体的に学ぶ生徒
心:ともに考え行動し、互いに高め合う生徒
体:心身を鍛え 困難に立ち向かう生徒
6 目指す教師の姿
(1) 子どもが安心できる教師
(2) 子どもと対等に向き合える教師
(3) 家庭・地域・同僚に信頼される教師
7 目指す学校の姿
(1) 生徒が楽しく生き生きと活動する学校
(2) 教職員が一丸となって取り組む学校
(3) 家庭・地域と連携し互いに協力する学校
8 経営の方針
「自己決定でき、自立した生徒を育てる教育」を目的に据え、「生徒が主役となって挑戦できる学校づくり」に取り組む。そのために、子ども(たち)が決めた目標に向かって試行錯誤する姿勢や、成否にこだわらず結果を受け入れて、次に向かおうとする姿勢を支援できるよう、「教える」「引き出す」「相談する」「協働する」という教師の役割を共通理解し、バランスよく使い分けて、自己決定や自己実現の過程を生徒ともに見通し、振り返りながら、生徒と向き合う。
9 学校経営の重点
(1)生徒指導の充実
家庭・地域および小中の連携を図りながら、全教職員の共通理解のもと、心の結びつきを柱に自尊感情の涵養に務める。
○ 生徒指導実践上の4視点(自己存在感の感受、共感的人間関係の育成、自己決定の場の提供、
安全・安心な風土の醸成)を生かした教育活動
○ 自己指導能力の育成
○ 生活の振り返りと見通しを持たせることの日常化
(2)体育・健康・安全教育の充実着
生徒一人一人が、学校や家庭および地域社会、そして将来において健康で安全・安心な生活が送れるよう、家庭・地域と連携しながら、心と体の健やか成長を育む教育の推進に努める。
○ 健康な生活習慣の確立
○ 健康相談活動の実施
○ 体力向上プログラム作成・実施
○ 各種たよりの発行などによる情報共有
○ 各種教室(思春期・情報モラル・薬物乱用防止)の実施
○ 交通安全指導の実施と危険区域の共有
○ 地域ぐるみでの防災訓練実施
(3)特別支援教育の充実
配慮を要する生徒についての理解に努め、日常的な情報交換を通して、個人および所属集団の成長につながるよう、適切な支援に努める。
○ 支援を要する生徒に関する配慮事項の共通理解
○ SC、SSWの計画的・有効的な活用
(4)授業の充実
「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善に取り組む中で、一人一人の子どもが、確かな学力を身に付けることができるよう、育成を目指す資質・能力を明確にするとともに、言語活動の充実を全教育活動の中で計画的・継続的に実践・改善しながら、個々の「能力・適性に応じた指導」と「学習習慣の育成」に努める。
○ どんな力を付けさせたいかを見通せる「単元の指導計画」の作成と実践
○ どんなことが分かったのかを確認できる振り返りやまとめの工夫
○ 生徒の多様な発想につながる課題の工夫
○ 小学校での既習事項(話型等)とのつながりを意識した、「根拠」や「理由」を明確に伝える
言語活動の充実
○ 目的に応じたICTの有効活用
○ 教科指導における出前授業の実施
(5)基礎的・基本的な知識および技能の定着
授業を通して身に付けた内容の定着機会を設けることによって、基礎的・基本的な知識および技能の確認や、活用への意欲喚起につながる取組に努める。
○ 基礎的・基本的な知識および技能の習得をねらいとした学習タイムの有効活用
○ 単元テストの効果的な取組と事後指導の充実
○ 個に応じた課題(宿題)の与え方の工夫(一人一台端末の活用)
○ 定期テスト前後の個別指導(学習計画立案および教科面談)を通して、自学自習できる生徒の育
成
○個に応じた模擬テストの活用
(6)道徳教育の充実
全教育活動を通して意図的・計画的な道徳教育を推進し、道徳性の育成に努める。
○ 自分の生き方について考えさせる授業、体験活動、講話等の実践
○ 思いやりの心を育む異年齢社との交流(縦割り活動、全校道徳)
○ 振り返りの場を大切にする教育活動
(7)特別活動の充実
学級集団を基盤に、生徒が自らの主体性を生かしながら身のまわりの課題を解決していく過程を通して、よりよい人間関係を築いていくことができるよう、必要な資質・能力の育成に努める。
○ 生徒の計画を生かしつつ、学校や生徒の実態に即した諸活動の推進
○ 話合い活動を通した意思決定の場の設定
○ 話合い活動を通した自治活動の推進
○ 互いに認め合い、助け合う心を醸成する集団づくり
○ 相互関係基盤を支えるルールやマナーの日常的な問い掛け
(8)地域を中心に据えたキャリア教育の充実
生徒一人一人が、学ぶことと自己の将来とのつながりを見通しながら、社会的・職業的に自立する力を身に付けるために、特別活動を要として必要な資質・能力の育成に努める。
○ 目的を明確にした体験事業・進路講話の活用・推進
○ 人権教育、金融・租税教育の実施
○ 地域行事への積極的参加
○ 9年間を見通した勤労観・職業観の育成
○ 自らキャリア形成に取り組むための情報提供
(9)校内研修の充実
学校課題解決に向けた共通理解を図り、校内研修を軸とした組織的・計画的・協働的な実践研究に努める。
○ 生徒の実態に即した、ねらいの明確な単元の指導計画の作成
○ 生徒の主体性を生かした授業への改善に向けた校内研修の充実
○ 「学習活動」におけるICTの有効活用に向けた校内研修
○ 校外研修への積極的参加
(10)家庭との連携強化
「すべては生徒のために」の共通理解のもと、積極的な情報共有を通して、協働体制で生徒の成長を支える環境を整える。
○ 各種行事の協働運営の推進
○ 休業日を利用した授業参観
○ 役員会兼保護者会での情報発信・共有
○ 全校三者面談の複数回実施
研究計画
1 研究主題
主体的に学ぶ生徒の育成
~個別最適な学びと協働的な学びの一体化を通して~
2 研究目標
個別最適な学びと協働的な学びの一体化によって、主体的に学ぶ生徒が育成されることを、実践を通して明らかにする。
3 研究仮説
主体的に学ぶ生徒は、基礎的・基本的な知識および技能を習得する個別最適な学びの場と、それらを活用して思考・判断・表現する協働的な学びの場の工夫によって、育成されるだろう。
4 研究内容
(1)個別最適な学びの工夫
- ICTを活用した授業づくりの工夫
- この学習到達度に応じた指導・支援の工夫
(2)協働的な学びの工夫
- 学習意欲を喚起する学習課題の設定
- ICTを活用した協働的な学びの工夫

外ヶ浜町役場 本庁
青森県東津軽郡 外ヶ浜町字蟹田高銅屋44番地2

外ヶ浜町役場 平舘支所
青森県東津軽郡 外ヶ浜町字平舘根岸小川251番地
外ヶ浜町平舘交流センター内

外ヶ浜町役場 三厩支所
青森県東津軽郡 外ヶ浜町字三厩新町18番地1