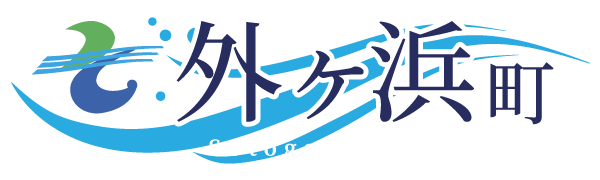文化財一覧
更新情報
| 2025年9月26日 | 文化財一覧を更新しました。 青森県大平山元遺跡出土品を追加しました。 |
|---|
文化財一覧詳細データ
詳細につきましては次のPDFファイルをご確認ください。
武者絵懸額
蟹田大平地区「大平八幡宮」に奉納されている幕末期の極彩色で描かれた大型の懸額です。
安政から文久にかけて、「大平村中」「大平若者」などによって奉納されています。
武者絵には、鎌倉武士を題材にし、「林泉」や「春信」等の作者名も記されています。
これらは、北陸地方、日本海側に多く見られるもので、北前船に関わりあり、その当時の交流や民間信仰が窺うことができます
付合い句懸額
「蟹田八幡宮」に俳句の上達を祈願し奉納された、俳句の技法のひとつ「付合い句」とよばれる俳句を選にはいったものを懸額しています。
嘉永年間に1面と文久年間に1面の計2面があり、願主は「松前城下瀬川屋甚作」「山内そのめ」とあり、幕末の動乱期にも俳句を嗜む人々がいたことを物語っています
漁労懸額
明治39年に遭難した鱈漁の乗組員が奉納したものです
赤平清兵衛塔
江戸末期の廻船業者「赤平清兵衛」の墓で、子息のひとりと伝わる「越中富山大郷屋清蔵」が安政2(1855)年に建立しました。
北前船で栄えた蟹田の偲ばせ、上方(北陸地方でしょうか)の石材が用いられています。
「塩越共同墓地」の中央に位置し、集落を見守っています。
蟹田奉行所跡
寛政年間におかれた奉行所の跡といわれています
外ケ浜道跡(あかふら峠)
松前藩が参勤交代に利用した道跡と伝わっています
鍛冶屋の一本松
「外ヶ浜町立蟹田小学校」前に立つ大きな黒松です。幹周りは4mを超え、高さは26mほどあり、樹齢500年ともいわれています。
古くは鍛冶屋がもっていた松のため、こう呼ばれています。
皀莢
住吉神社の御神木で中部地方より南に生息するマメ科の植物大阪から勧請したことを物語っています
専念寺山門と仁王尊像
蟹田「専念寺」の山門、古くは鐘楼をかねていましたが、半鐘は役目を終え、本殿の前に建っています。
安政年間に建築されたと伝わっています。「専念寺山門」に安置されている仁王尊像です。
隣り村蓬田広瀬の「安田和尚」の作と伝わり、1体の頭部を仕上げ、これを背負ってニシン漁がさかんであった北海道へ渡り、寄進を仰ぎ像を完成させたといいます。
比較的あらたしいもので、明治時代に刻まれた秀作です。
外ケ浜道跡(観瀾山下)
松前藩が参勤交代に利用した道跡と伝わっています
東風留舘跡
安東水軍が舘を構えたと伝えられる
観音菩薩坐像
江戸時代前期の寛文6(1666)年、蝦夷地からもどった円空が彫ったものです。
一刀彫りによるもので、荒削りですが繊細さがあります、こちょこちょ様として住民に愛されたため、全体が摩耗しています。
平舘「福昌寺」に安置されています。
推定樹齢600年の黒松 長寿の松
松前藩が参勤交代に利用した道跡沿いの松並木の中にある樹齢600年といわれる黒松
夫婦松
松前藩が参勤交代に利用した道跡沿いの松並木の中にある赤松と黒松が夫婦のように並んでいるためこう呼ばれています。
藤嶋の藤
樹齢250年以上といわれ、高さ15m幹周は1.5mの藤の木です
荒馬
木製の馬首を胸部の前にくるように構えた男1名と手綱取りの女1名が1組となって踊り、荒ぶる馬を静めるような芸能です。
囃子に笛と太鼓、近年になって手平鉦がくわわっています。
サナブリ行事の行列踊りのひとつでしたが、いつの頃からその踊りが分散し、昭和の初期頃から夏のネブタ祭りに披露されることとなったようです。
古くは各地域にありましたが、三厩増川地区で伝承しているものです。
太刀振
竹の棒を太刀にみたて、笛・太鼓にあわせ二人一組で棒を打ちあわせながら踊る、五穀豊穣を願うものです。
囃子に笛と太鼓、近年になって手平鉦がくわわっています。サナブリ行事の行列踊りのひとつでしたが、いつの頃からその踊りが分散し、昭和の初期頃から夏のネブタ祭りに披露されることとなったようです。
古くは各地域にありましたが、旧宇鉄村(三厩六條間地区)にのみ残っているものです。太刀については、竹棹や稲の穂、農耕具、錫杖ともいわれています。
平舘陣屋跡(お仮屋)
嘉永元(1848)年に築場された「平舘台場」を警備するための藩士の屯営として、翌年に設けられました。
7反20歩(約7000㎡)、南東北3方に6尺(約1.8m)土塀、6~70名が勤務し、20~25名交代したといわれています。
当時の縄張りが確認でき、掘跡も一部残っています。構築した年代、県史跡「平舘台場跡」もあり、古い絵図とも合致し、往時の様子がよくわかります。
観世音菩薩像
県指定 円空による寛文7年頃に彫った木像の観世音菩薩像。
平舘台場
嘉永元年に築かれる 県史跡指定(2004年4月19日) 嘉永2(1849)年に築かれた、大砲を据え付け海防に備えた砲台「台場」があります。
江戸時代後期、異国船の動きが激しくなると、弘前藩も対応をせまられ、竜飛崎、高野崎等へ台場を設け、海岸の警備にあたりました。
それらのほとんどは高台にありますが、この「平舘台場」は、県内には珍しく、平地に設けられました。
西洋風と呼ばれ、高さ1.5m、幅10mの土塁が扇形をなし、東西11m、南北80mに区画、7カ所の窪みに大筒を設置したものです。
しかし、開国後は、台場の重要性は薄れ、明治9(1876)年頃には廃止されています。
青森県大平山元遺跡出土品
北東北地方における後期旧石器時代後半から縄文時代初頭に至るまでの石器組成と土器出現を含む道具構成の変遷過程と石器製作技術をよく示し、縄文時代への移行の在り方を考究する上でも重要であり学術的価値が高いものとなっております。
大平山元遺跡
旧石器時代から縄文時代のはじめまでの石器の変遷が追え、各地との交流も見ることができる石器原産地に近接した遺跡です
宇鉄遺跡出土品
弥生時代中期の土器、石器類、玉類。碧玉製管玉が特徴的です。
遺跡は三厩地区の海岸段丘にある縄文時代晩期を中心とした遺跡です。

外ヶ浜町役場 本庁
青森県東津軽郡 外ヶ浜町字蟹田高銅屋44番地2

外ヶ浜町役場 平舘支所
青森県東津軽郡 外ヶ浜町字平舘根岸小川251番地
外ヶ浜町平舘交流センター内

外ヶ浜町役場 三厩支所
青森県東津軽郡 外ヶ浜町字三厩新町18番地1